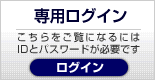モバイルサイトにアクセス!
福島県福島市大町2-5
TEL.024-521-1635
FAX.024-505-0115
基本資料
2024年度 基本方針・事業計画
【はじめに】
青年会議所にしかできない運動とは何でしょうか。先輩諸氏がこの日本で青年会議所を立ち上げたのは戦後間もない頃でした。荒廃した国土の中で「新日本の再建は我々青年の仕事である」といった志のもと、青年会議所はその運動を開始しました。立上げから約75年、青年会議所は世の中の変化に合わせ、様々な社会課題の解決に取り組んできました。
加速度的に変化をしていく時代の中で何を目的に掲げて運動を展開していくのか。マクロ的視点でみれば、国内経済の充実が万人の幸せに繋がることであり、更に、国際経済との密接なる連携は欠かせないことです。ミクロ的視点で見れば、地域が抱える課題を正確に捉えながら、未来を見据え、どうような手を打つべきなのかを考えて行動に移していくことが肝要です。
先々の時代を予見し、時流に合わせた社会課題の解決に取り組むことのできる組織で有り続けるべく、私たちは率先して学び、変化と発展をし続けていかなければなりません。
【伝統文化の継承】
福島市の夏祭りである福島わらじまつりの日は、市民が一堂に会しているのではないかと驚きを感じるほど、多くの人々が参加し、まちに笑顔が溢れます。福島駅前は熱気に溢れ、まるで異空間を訪れているようなまつり独特の雰囲気が作り出されます。それが福島市の文化であり、市民から最も愛されている夏祭り、「福島わらじまつり」です。現在では東北絆まつりの一端を担い、福島わらじまつりは県を代表するまつりとして全国的にもその知名度を高めました。
これからは、この伝統文化の価値と魅力をメンバーそれぞれが改めて理解し、次世代に継承する仕組みを対内外で整えていくことが必要だと考えます。そして、若年層が継続して関心を持ち、次世代の担い手となってもらうために、積極的にまつりに参加してもらえるような運動を展開することで、この伝統文化を継承していきます。
これらの取り組みにより、伝統文化が若年層に対してより響くものとなり、ひいては福島の未来を築く力となっていくことを確信しています。
【多様性と持続可能な組織】
青年会議所の一番の強みは、性別、国籍、政治、宗教、文化背景に左右されることのない自由な意思に基づき、多様なメンバーが共に活動することを掲げている点だと考えます。以前、例会の講演会の中で印象に残った言葉があります。「青年会議所は社会と非常に似た構造になっている。」この言葉がとても私の頭に残りました。社会は日々刻々と変化しており、青年会議所も同様に変化をしています。メンバーそれぞれの強みやアイデアを十分に活用することができれば、創造的で柔軟かつ持続可能な組織を目指すことができると考えております。
固定観念に縛られ何も変化をしないのではなく、新しい形を常に模索することこそが一番の進化だと考えます。
【国際化推進・文化や視点の違い】
2003年、日本は観光立国宣言を行っています。それから20年有余年、全国的に見ると人口に対する在留外国人の割合は2%を超えました。福島県・福島市に関しては未だ1%に満たない現状です。これは今後の少子高齢化社会を考えた上で、私たちが抱える大きな課題だと捉えています。私は、福島青年会議所創立55周年の時に、姉妹JCである南投國際青年商會に記念式典の案内状をお届ける機会を頂き、その時に初めて台湾を訪れました。それ以来、個人的な機会を合わせると毎年台湾を訪れているのですが、訪れる度、普段は当たり前に感じている日本の良さを発見することができるのと同時に、活気と笑顔と希望に溢れる異国の若者に出会い気力を高めることができます。
異文化との交流は、自分の「当たり前」を壊し、新たな気付きを授かることのできる貴重な機会です。国際的な文化や習慣の違いを肌で感じることができる事業を開催することで、異文化交流を推進し、新しい気付きや価値観が生まれることを目指します。
さらに、福島青年会議所としても国際的な繋がりを構築し、世界の青年会議所と連携しながら情報交換を行うことで、組織の国際化を推進していきます。
【豊かなまちづくりと地域資源再活用】
福島には豊かな自然や美味しい食べ物が数多くあります。13年連続水質日本一を獲得している一級河川荒川をはじめ、綺麗な環境の下で育まれた食べ物の質は、都市部に負けない誇るべきものです。周囲を見渡せば山々が連なり、土湯や飯坂や高湯をはじめとする数多くの温泉地があります。福島は自然が豊かな地域です。魅力というものは、内なる視点では見えなくても、ひとたび外から見てみると驚き感動を生むものであるということが往々にしてあります。この豊かな自然や地域資源を再構築(リブランディング)する取り組みを行い、県内外の方々にこのまちの良さを感じて頂く機会を創出します。
【デジタル技術と情報リテラシー】
デジタル技術の活用は、現代社会において必要不可欠です。福島青年会議所としても、デジタル技術を活用した地域の課題解決やイノベーション創出に向けた取り組みをサポートし、地域社会の発展に貢献します。また、福島青年会議所の活動の効率化や情報に関するITリテラシーを高めるために、メンバーにもこれらを学び直す機会を提供し、デジタル技術の急速な発展に対応していくことを目指します。
【メンバーを増やす会員拡大】
福島青年会議所のメンバーは年々減少しています。辞めていく要因は様々です。ですが、私がひとつ信じていることは、青年会議所が行う運動は、素晴らしいということです。社会同様に多様な人間が集まるからこそ議論は紛糾し、価値観と志向をぶつけ合わせることができます。時にぶつかり合うことは、成長のために必要なことです。多様な価値観を財産として捉えつつ、その上で、会員数を増やしていくためには、メンバーの素養の向上を兼ねた会員拡大が必要不可欠になります。
【結びに】
私が19歳の頃、孫正義氏の漫画版自伝を読み、熱く感動したことを思い出しました。孫氏曰く、これからはコンピューターの時代だということを知り、いまから40年以上前に16歳で単身渡米し、その経験を元手に会社を起しました。その行動力の速さと世の中のトレンドを見る力。今や誰しもが知る会社を起しながらも、未だに挑戦を忘れないその心を持ち続ける姿勢。それらを可能にしているのは一体何なのか。それは、大きな志です。「情報革命を通じ、人々をより豊かにする。」がむしゃらに行動し続けていくその先には、単純なお金稼ぎではなく、社会貢献や自分自身の志・夢・目標とのリンクが非常に大事になると感じます。
2022年のイグノーベル賞にて成功というものは運の要素が多い「社会的な成功において重要なのは「才能」よりも「運」であることの数学的な証明」という論文が発表されました。成功の確率を上げるためには、前述の孫氏においても共通点があります。それは相当な試行回数を増やしているという点です。全てのことで言えることですが、特に青年会議所は1年間という短い時間の中で運動を展開していくため、何かにつけ前年踏襲が一番だと考えている時点で1年間はあっという間に過ぎていってしまいます。解決を求められている問題に対し、その原因を追究し、的確かつ具体的な解決策を提案し、実行し、その価値を検証するプロセスこそが青年会議所の事業の醍醐味です。前年踏襲を当たり前にするのではなく、原初の目的に立ち返り、受容と排斥のバランスを考えていくことが必要ではないでしょうか。人生は思った以上に短く、あっという間に終わると思います。その中で青年会議所の1年間は瞬きのような期間です。 「必ず行動してみること」頭の片隅にしまってしまった言葉だと思いましたが、こうして理事長所信を書きながら、人生を振り返った時に大事なことを思い出しました。
青年会議所は、各地の毎年異なる理事長や会長が手帳の色のように全く違う色でもって運動を展開していきますが、確かにそこにあるものは、みんなが「明るい豊かな社会の実現」を目標にしているということです。
私は、この青年会議所を通じて知り合えた人たちとの絆をフルに活用し、地域、メンバーに還元できる運動をこの1年間展開していきます。
私たちは常に新しくあるために、その時代のメンバーがそれぞれあるべき姿、その時代に求められるものを自ら考えて行動していくことが大切です。今後も福島青年会議所が地域社会の発展に寄与し続ける存在となるため、学び続け行動に移すことで、新たな価値を創造していくことができると信じています。
志高く 孫 正義
「社会的な成功において重要なのは「才能」よりも「運」であることの数学的な証明」 2022年※イグノーベル賞
※世界中のさまざまな分野の研究や発明の中から「人々を笑わせ、そして考えさせる業績」に対して贈られる賞。